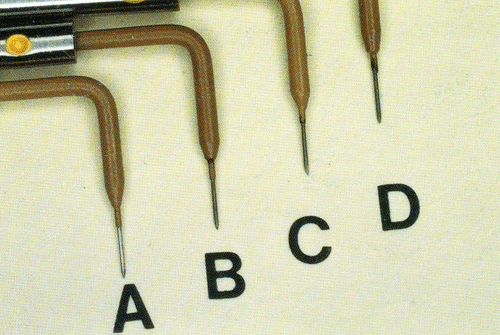日本医学脱毛学会
Japanese Society of Hair Surgery & Medicine
前期6単位)患者と脱毛トラブルの予防
a. 患者指導
b. 脱毛中の患者への対応
c. 脱毛術トラブルの予防と対策
トラブル例
• 熱傷
• 凍傷
• 色素沈着
• 埋没毛
• 毛嚢炎
• リンパ腺障害
• 内出血
• その他
___________________________________________________________
脱毛中の注意事項
a. 患者に不安を与える言動は謹みます。
b. 信頼関係が持てるように務め、コミュニケーションを取るようにします。
c. 患者に対して2名の術者で脱毛を行なう場合、術者同志で必要以上の会話は避けます(特に私的な会話は避ける)。もし会話を持つなら、患者を含めた会話とすべきです。
d. 脱毛中に席を立つ場合は、必ずニードルホルダーをス−パークリップに固定してから、席を離れるようにします。
e. 通電後、毛が抜け難い場合は、以下が考えられます。
1)針の刺入方向が間違っていて、毛根・毛球に沿っていない(毛球・毛乳頭部が的確に破壊されない。
2)休止期の短い毛の脱毛時などで、電気凝固された範囲が深か過ぎて、浅い毛包の多くの部分が温存されている。(スライド通電の技術が必要)
3)とくに絶縁部が1〜1.5mmの長めの脱毛針などを使用時、毛球部は電気凝固されても、毛包上部で毛小皮と鞘小皮との咬み合わせが温存されています。(同様にスライド通電の技術が必要)
4)通電が弱い場合や、または通電されていない場合。患者から脱毛途中に痛みがなくなったとの訴えがあったり、皮膚反応が弱くなったりして、これに気付く事もあります。このような理由で脱毛中は患者に対し、痛みの度合いの問いかけや確認、皮膚状態の把握を怠らないようにしなければなりません。
電気が通じていないのには次のような場合が考えられます。
ア)ニードルホルダーや対極板のプラグがゆるんでいるか、はずれている。
イ)コードのハンダ付け部における断線。
ウ)コード内での断線。
ヱ)イ)は確認は容易です。ア)イ)が認められなければ、ウ)が考えられます
毎回、脱毛前にニードルホルダーと対極板のコード内断線をテスター等でチェックするのが望ましい。
下肢部脱毛後の注意事項
a. 脱毛後、脱毛部に一致して皮内熱反応による小丘疹(小さな扁平なふくらみ)が2〜3日続きます。したがって、患者には脱毛直後は皮膚が多少凸凹していますが、2〜3日すれば平らになる事を、説明しておきます。(氷冷却法脱毛術)
b. 脱毛部(小丘疹)に一致した点状の発赤も4〜5日でほとんど気にならなくなります。ごくまれに1ヶ月前後継続することがありますが、その後は薄くなっていきます。(氷冷却法脱毛術)
c. 局所麻酔を行なった場合は、紫色の内出血が約1ヶ月続く場合がありますが、その後消失します。また、脱毛後の皮内反応も氷冷却法脱毛術よりも強い。
d. ごくまれに、脱毛部位の皮膚表面に触れると「ピリピリ」する感じが 1〜2ヶ月位続く患者も診られますが、その後消失します。
e. まれに脱毛後数日してから「痒み」を訴える患者がありますが。皮内の点状熱傷の治癒過程の現象で、1〜2週間で消失します。
f. 下肢毛がほぼ永久脱毛された状態になると、特に冬季に脱毛部位が乾燥しやすくなります。ビタミンA、E、クリームなどの外用が冬季には必要になる事があります。
以上の様な事を患者に充分に説明をしておきます。
皮膚トラブルを防ぐために
a. 使用する対極板は脱毛部近くに位置させます。ただし、胸部・背部の脱毛時は心拍系への影響を防ぐ為に、対極板は腕に置き、電流をその方向に流すようにします。また、対極板は必ず皮膚に広く密着させ、熱傷が生じないように注意します。なお、心臓ペースメーカーを入れている患者や心臓疾患を持つ患者は絶縁針脱毛術は行ないません。歯科矯正している方は、常に違和感が無いか注意して行ないます。出来れば矯正が終わってからに行なうのが望ましいと思われます。
b. 毛が太ければ太めの針を、細ければ細めの針を使用します。小耳症の耳、女性の顔面、前腕部の細い毛などに対して、太いC・K・L型針を使う事は点状瘢痕を作りやすいので厳禁です。
c. 毛の下側から針を毛根に沿って進め、針基部の絶縁までを皮内に刺入した後に通電します。この際、皮膚をへこまさないように、又は針先を持ち上げたり、浮かせたりしないように注意します。特にねている(毛根傾斜の小さい)硬毛の太いC(K)型針などで脱毛する場合(腋毛前腕部とか下肢の硬毛)は刺入後、針先を少し下方に下げ、皮内の針先が皮膚面から遠ざけるようにした後に通電します。ただし、U・S・L型針では、ねている硬毛でも針刺入後、針先を下げずにそのまま通電します。
d. 毛深い(毛の間隔が密な)場合は、間引き脱毛を行なうのが原則です。脇やビキニラインで毛深い患者は第1回目、顔面・小耳症などでは初めの2〜3回は、間引き脱毛します。
e. 脱毛中は絶縁状態に常に留意し、付着物を酒精綿にて拭き取る時は、拡大鏡で必ずチェックをします。そして、その状態に応じた脱毛テクニックを用います。
写真(絶縁が剥離した針)
A: 使用前の絶縁針
B: 基部の絶縁が黒く剥離している。この部分は
皮膚に触れるところなので、新しい針に変え
る必要がある。
C: 絶縁先端部が黒く剥離しはじめているが、基
部の絶縁は剥離していないので、まだ使用が
可能である。
D: Cの状態が進んで針基部近くまで黒くなってい
る。使用中止とする。
f. 皮膚状態(皮膚の発赤・腫脹および熱感など)に注意し、特に熱感が強い場合は脱毛中でも即座に冷却処置して、その軽減に務めます。また、脱毛時における皮膚反応が強い場合は、通電時間を短くするか、出力を下げるのが原則です。
g. 腋窩の脱毛時、腋窩神経に針先が触れたまま通電すると手の先がしびれます。これを防ぐために、腋窩神経の走行部(腋窩動脈の拍動に沿った線)に印をした後、手指で上または下に皮膚を引っ張り、針先が神経から離れるように通電します。
h. 必ず、術者はペンを持っている事。現在まで、1例の患者で針が折れて皮内に残留した報告があります。もし、針の皮内残留が起こった場合は、冷静にボールペンにて○印で囲んでおけば、事後の針の取出しは容易です。
絶縁針の痛み具合による使用可否
1)移行部が輪状に黒くなっている。
2)移行部と絶縁先端部が黒くなっている。
3)絶縁部がほとんど黒くなっている。
4)絶縁部が削られている。
5)絶縁部が途中まで黒くなっている。
6)使用可能(痛み無し)
5)のみ押し込むようにして、脱毛可能
ですが研修者は不可とします。